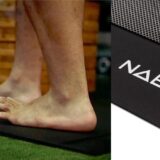はじめに:なぜ、うまくいく人といかない人がいるのか?
筋力トレーニングは、多くの人にとって「必要」とされながらも、「うまくいかない」例も少なくありません。
同じような疾患を抱えていても、結果に差が出るのはなぜでしょうか?
今回ご紹介するのは、肩・膝・腰の3つの異なるケースです。
それぞれの方に共通していたのは、ある「工夫」を加えたこと。
それが、回復の分かれ道になっていました。
ケース1:肩の人工関節手術後、肩を動かすのが怖かった62歳女性
【登場人物】高野美菜子さん(仮名・62歳・TSA後)
「痛みがないのに、肩を上げられない」
術後の経過は順調でも、肩に手が届かず日常生活が不自由だった高野さん。
リハビリ初期は、恐怖感と過緊張が強く、代償動作も出やすい状態でした。
分かれ道となったのは、
・難しい訓練(肩関節回旋の筋力トレーニング)は、理学療法士の監修を徹底したこと
・日常生活場面で、腕だけではなく、肩甲骨と体幹を一体で動かす工夫
・痛い時から使うことが出来るトレーニング道具を選んたこと→「できること」から始め、小さな成功体験を積み重ねた
詳細はこちらの記事で:
> 肩TSA後のリハビリで動きが戻った理由|高野美菜子さんのケース
ケース2:人工膝関節の手術後、動けないままだった65歳女性
【登場人物】後藤かなえさん(仮名・65歳・TKA後)
「手術すれば歩けると思ってたのに、全然動けない…」
TKA(人工膝関節全置換術)を受けた後も、膝裏の痛みと屈曲制限が残ってしまい、外出もままならなかった後藤さん。
防御的な筋の緊張が強く、痛みに対する不安も重なっていました。
分かれ道となったのは、
・膝周囲だけでなく、股関節や体幹を含めた連動トレーニング
・一人でできる「安全な動き(チェアスクワットなど)」の反復
・日常での役割を自然にこなしているうちに回復してきた(孫とブランコに乗った)
詳細はこちらの記事で:
> TKA術後に笑顔を取り戻した理由|後藤かなえさんのケース
ケース3:高校時代の腰椎分離症から、社会人10年目で活きた経験
【登場人物】吉田裕作さん(仮名・32歳・元社会人野球選手)
「また動けなくなるかも、という不安がずっとあった」
高校時代に腰椎分離症を発症し、思うように野球が出来ない時期が長く続いた吉田さん。
しかし社会人になってからも、腰の痛みや不安定性と常に向き合い競技を続けました。
分かれ道となったのは、
・腹圧(インナーユニット)と体幹の安定性に目を向けた点
・痛みのためのトレーニング道具を使用してこまめにセルフケアを行ったこと
・野球指導者としての道に進む、という目標設定
詳細はこちらの記事で:
> 腰椎分離症からの復帰とその後|吉田裕作さんのケース
筋トレが「成功」した人たちに共通していたこと
これら3つの事例に共通していたのは、以下のような要素でした:
- ただ患部をケアするだけでなく、周辺の関節や全身的な動きを見直した
- 自分の身体に合ったセルフエクササイズ方法を見つけて、主体的に続けることができた
- 独学ではなく、療法士やトレーナーと協力してリハビリを継続した
筋トレの成否は、筋肉の太さだけで決まるわけではありません。
その人の背景、生活環境、心の動きを見極め、「ひと工夫」することが成功を後押しします。
おわりに:あなたにとっての‟成功の分かれ道”は?
体を動かすのが怖い、筋トレで効果が出ないーー
そんなときは、「その方法がたまたま合っていない」だけかもしれません。
助けてくれる方と積極的にコミュニケーションをとり、自分と向き合うことで、必ずあなたにとっての“分かれ道”が目の前に現れると思います。ぜひ、事例をヒントにしてみてください。
 4 Unique Steps
4 Unique Steps