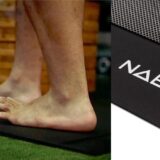──イメージと現実、科学で読み解く“リリース”の正体
はじめに
『筋膜リリース』というリハビリテーションの方法が、非常に効果的であることは今では疑う余地はありません。
ところが、「筋膜リリース」という言葉を聞くと、「筋膜がくっついている」「癒着している」から、それを“剥がす”というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか?
これに対し、基礎医学や医療、リハビリテーションの現場では「筋膜って、ほんとうに剥がせるの?」という声も少なくありません。
この記事では、筋膜リリースの本当の意味と、科学的に分かってきた“実際の効果”について、わかりやすくご紹介します。
筋膜とは?──身体を覆う“第二の骨格”
筋膜(ファシア)は、筋肉、臓器、血管、神経などを包むネット状の結合組織で、全身を立体的につないでいます。
その主成分はコラーゲンで、弾力があり、構造を維持しながらもある程度の柔軟性を持ち合わせています。
筋膜には以下のような役割があります:
- 身体の構造を保つ(姿勢や動きの土台)
- 筋肉の滑走を助ける
- 痛みや動作の感覚に関与
- トリガーポイントの発生源にもなる
「筋膜を剥がす」は本当にできるのか?
結論:
物理的に“筋膜を剥がす”ことは、科学的にはほぼ不可能
2008年のChaudhryらの研究では、筋膜を1%変形させるには約90kgfの力が必要とされています。
フォームローラーや手技では、せいぜい10kgf前後の圧しかかからず、深層筋膜には届かないとされています。
※参照:Chaudhry H. et al., Journal of the American Osteopathic Association, 2008
つまり、「筋膜を剥がす」「溶かす」といった表現は、実際の組織変化としては非現実的です。
では、なぜ「軽くなった」「効いた」と感じるのか?
その答えは、「神経・感覚・循環系の変化」にあります。
- 神経への刺激:筋膜には多くの感覚受容器があり、軽い刺激で緊張緩和・副交感神経優位などの反応が生じます。
- 滑走性と血流改善:筋膜と筋肉の滑走がスムーズになることで、血流が改善し、可動域や動作感が向上します。
- 感覚の再構築(中枢反応):身体感覚が一時的にリセットされ、「整った」「ほぐれた」と感じやすくなります。
- プラセボ効果:信じて行うことで、身体が自然に反応する心理的要素もあります。
これらはすべて、“構造”ではなく“機能”の変化であり、筋膜リリースが「神経生理学的介入」であることを示しています。
「剥がせる」と言われてきた理由とその誤解
一部の手技療法では、「癒着を剥がす」という表現が使われてきました。
しかし、現在の研究ではそのような変化を短時間で実現する証拠は乏しく、あくまで比喩的な表現にとどまるとされています。
とはいえ、一部の文献では以下のような可能性にも触れています:
- Steccoら(2011):長期的な張力によって筋膜構造がリモデリング(再構築)されることがある
- Langevinら(2004):慢性腰痛患者では、筋膜組織が肥厚・滑走性低下している様子が画像で観察された→筋膜の滑走障害が持続する痛みや運動制限と関係する可能性を示唆しており、筋膜の柔軟性や動きやすさを保つケアの重要性を裏づける
こうした変化は、何ヶ月〜年単位の力学的刺激による組織適応であり、フォームローラーや短時間の手技で「剥がれる」ような即時的な構造変化ではありません。
セルフ筋膜リリースの方法と注意点
『筋膜リリース』の名称には様々な研究が進められている最中ではありますが、筋膜リリースという方法自体は、非常に効果的な手段であることは間違いありません。
一例を示します。

例:背中のフォームローラー
- 床に座り、背中にローラーを置き上下に転がす
- まずは5分間から、呼吸を止めず、痛気持ちいい程度で行う
おすすめセルフケアツール:トリガーポイント グリッドフォームローラー(Mueller Japan)
セルフ筋膜リリースを安全かつ効果的に行いたい方には、Mueller Japanの「トリガーポイント グリッドフォームローラー」がおすすめです。

送料無料
この製品は、筋膜の滑走性を高める凹凸構造と適度な硬度設計により、
- 表在感覚への刺激
- 血流促進
- 神経系リラックス
といった機能的な効果を引き出しやすく、解剖学とリハビリ知見を背景に設計された信頼性の高いケアツールです。
軽量・コンパクトで使いやすく、医療・フィットネス現場でも幅広く採用されています。
注意点:
- 強く押しすぎない(青あざはNG)
- 神経が敏感な方、線維筋痛症の方は慎重に
- やりすぎは逆効果。1日1部位、数分までが基本
まとめ:剥がすのではなく、「整える」ことが目的
筋膜リリースとは、“筋膜を剥がす”のではなく、“神経・感覚・滑走性を整える”ためのケアです。
「剥がす」というイメージにとらわれすぎると、強刺激や無理なケアにつながりかねません。
やさしい刺激で、今の自分の身体と対話しながら“整える”意識こそが、筋膜リリースの本質といえるでしょう。
参考文献
- Chaudhry H., Schleip R., et al. (2008).
Three-Dimensional Mathematical Model for Deformation of Human Fascia.
Journal of the American Osteopathic Association, 108(8), 379–390. - Schleip R. (2003).
Fascial plasticity – a new neurobiological explanation.
Journal of Bodywork and Movement Therapies, 7(1), 11–19. - Wilke J. et al. (2019).
Myofascial chains: fact or fiction?
Journal of Anatomy, 234(6), 838–850. - Stecco C. et al. (2011).
The anatomical and functional relation between gluteus maximus and fascia lata.
Journal of Bodywork and Movement Therapies, 15(2), 127–132. - Langevin H.M. et al. (2004).
Ultrasound evidence of altered lumbar connective tissue structure in chronic low back pain patients.
BMC Musculoskeletal Disorders, 5:29.
 4 Unique Steps
4 Unique Steps